こんにちは、Kohです。当ページにアクセスいただきありがとうございます。
育児をされている全国のみなさま、大変お疲れ様でございます。
今の日本では、「子育て無理ゲー社会」と言われるくらい
「子育てしづらい」という認識が浸透するようになってしまいましたね。
少子高齢化という実態、日本の子育て政策や、保育園や幼稚園、小中高の学校等のシステム等々
現代子育て世帯に立ちはばかる壁は数知れず。
結婚や出産・子育てに躊躇してしまう若者も。
私も、少し前は自分が子育てをするイメージは全くありませんでした。
しかし、実際してみて思いました。
独身より家族がいた方がいい。
こんな時代でも育児は楽しい。
今回は、今の時代で子育てを楽しめるような考え方を記したいと思います。
シンプルな毎日が平和であること

とにかく、子どもといると平和です。

は?子育て大変すぎて平和じゃないよ
と考えている方もいらっしゃると思います。
日々の寝不足、話せない子どもと1日中いること、社会的な疎外感。
育児ノイローゼはこういった原因でなってしまいます。
私は、子どもがいるその環境を「逆手にとって」考えて、
とても平和だと感じるのです。
どういうことでしょうか?
例えば、遊ぶ場所。
子どもと遊びに出かけるときは、
大体公園だったり、支援センターやプレイグラウンド等
子ども向けの遊具やおもちゃがある場所に行きますよね。
そういうところに行って、
子どもたちが無邪気に遊ぶのを見て感じるのです。



平和だ・・・
と。
また、赤ちゃんがすくすく育っていくのを見ると
人間の成長の過程を身近に見ることができて、
とても不思議な気持ちになることがあります。
人の成長を間近で見るのは、
自分にとってとてもいい刺激になります。
要は、「色んな事をシンプルに受け止めることができる」んです。
一方、独身時代は、たしかに自分の好きな場所に行けて、
好きな食べ物を食べれて好きなだけお酒を飲めたりしたけど、
その分感じてしまう「生きづらさ」や「複雑さ」があります。
人間関係や恋愛で人に気遣うことや、
何かあったら一喜一憂したりすることや
嫉妬、マウント、人の悪口、etc.
「大人の世界」ならではのめんどくさいことって
たくさんあるじゃないですか。
アルコール無駄に飲んで二日酔いしたり
無駄なお金が出てったり…。
(あっそれは私がいけないというお言葉はお口チャックでおなしゃすっ)
(上記のこととは無縁な若者はもはや菩薩級にすごい)
そういう日々も楽しかったけど、混沌だったなと思います・・
今は自分の家族や自分に「集中できる」時期であるんだと
こういう平和な環境を享受しよう
そう考えています。
「他人と比べない力」が身につく


子育てをすると、この単語をかなり頻繁に目の当たりにするでしょう。
「個人差」
赤ちゃんの体重、成長度合い、ミルクの飲み方、泣き止まない・・
子育ては色んな悩みがつきものになります。
しかしながら、これらの悩みのたいていのことは
「赤ちゃんの個人差」
なんです。
ミルク飲む・飲まないのも赤ちゃんの個人差
抱っこしてなきゃ泣いちゃう赤ちゃん・すぐ寝てくれる赤ちゃんも個人差
言葉が早く話せる・全然話せないのも個人差
あらゆる症状や成長が、子どもにとってケースバイケース。
だから、基本は「他の子どもと比べずに」「気長に見守ってあげること」が
悩み解決には一番手っ取り早かったりします。
こういったマインドが身につけられるようになると、
大人の世界ではびこっていた
「他人と比べる」
ということをしなくなります。
他人の言うことが気にならなくなります。
これは、独身時代や、大人だけの世界にいたら
決して身につかなかったことだなと感じます。
もちろん、子どもがいない方も、
他人と比べないことができる方はいると思います。
私の場合は、子育てをすることで
「他人と比べない力」を身に着けることができて、
自分の人生はすごい豊かになったと思います。
子どもから学べることって、本当に多いですよ^^
SNSに飛び出せば「孤育て」から抜け出せる


「文明の利器」を駆使しましょう。
「孤育て」を感じているなら、
同じように感じている人たちと交流をしてみましょう。
一番手っ取り早い手段は、ご存じのとおり、SNSです。
今は、TwitterやInstagramが主流ですよね。
インターネットやSNSの広い世界に飛び出すのは
多少躊躇してしまうかもしれませんが、
必ずあなたに共感してくれる方はいらっしゃいますし、
あなたと同じようなニーズを抱えている方もいらっしゃいます。
また、アウトプットをすることによって
ストレスを軽減させることができます。
私の場合、うつ病のとき心療内科に通っていましたが、
書いたりアウトプットすることによって
ストレスが軽減されるというお話を聞きました。
なので私はその時感じたことや辛いことを
そのままノートに書き写したり
Twitterを使って頭の整理をしたり
積極的にアウトプットするように努めました。
SNSは誹謗中傷がひどい問題があるから怖いよ
と思う方もいらっしゃると思います。
誹謗中傷自体はもちろん言語道断です。
とはいえ、誹謗中傷するのは
だいたい暇な人がインフルエンサーに対して
ウザがらみをするのがほとんだと思いますので、
ある程度の節度を守れば、
誹謗中傷されるリスクはあまり感じる必要はありません。
インターネットやSNSは、現代ならではのメリットです。
使わない手はありません。
積極的に活用して、子育てを楽しくしていけるといいですね!
さいごに-「無条件で私を愛してくれるひと」-


これは時代、場所を問わず共通していることですが、
「あなたを無条件で愛してくれるひと」がいます。
それは、あなたの子どもたちです。
大人の人間関係は、何かと「条件付き」であることが多いですよね。
愛される方法、好かれる方法、見た目、態度、等々。
そんな言葉をよく見ますが、
そういう「条件付き」の付き合いをすると、
なんだか薄っぺらく見えてしまいます。
子どもはそういうのを一切なしで自分のことを見てくれるので
心の拠り所ができます。
今は子どもと向き合って辛い時期でも、
いつかそういう「満たされる」気持ちは必ず訪れると思います。
それは、何よりの精神安定剤になると思います。
子どもが大人になったとき、
そのような「無条件な愛」が無くなってしまうかもしれません。
「何かをできない理由」を子育てのせいにすると
幸せでなくなってしまいます。
子育てをしても「何かできるようになるためにはどうしたらいいか」
ということを考え、行動すれば
きっと答えは出ると思いますし、幸福度も爆上がりします。
日本での子育てが幸せなものになりますように。
ではまたっ!


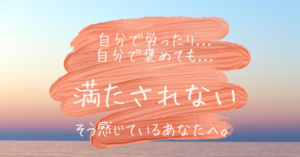


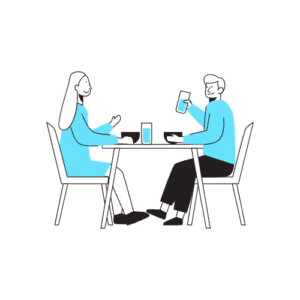




コメント